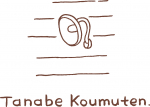コラム
プランニング
2025.09.08
外構リフォームのすすめ~よりよい暮らしのために~

外構のリフォームと言えば、まずはフェンスや門扉などのエクステリア製品を新しくすることを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
製品を新しくしてデザイン性や耐久性を向上させることも大切なことですが、暮らしを快適にするためのもう少し踏み込んだリフォームもぜひご検討いただきたいと思います。
暮らしをよりよくするための外構リフォームについて、当社の施工事例と共にご紹介していきます。
暮らしの不便を解消する外構リフォーム
□玄関までの動線が悪い
□雑草のお手入れが大変
□インターフォンや郵便ポストが使いにくい
など暮らしの中でのちょっとした不便はありませんか。
諦めずに一つずつリフォームで解決していきましょう。


防犯を意識した外構リフォーム
空き巣などの犯罪に巻き込まれないためには、まずは犯罪者が侵入しにくい外構にする必要があります。
□防犯カメラの設置
□侵入しにくい窓の設置
などで防犯意識の高い家だと思わせることが有効です。


ライフスタイルの変化に合わせた外構リフォーム
住む人の家族構成や年齢などの変化によって、ライフスタイルも変わっていきます。
庭や外構にも新たな役割を持たせて、毎日をより楽しく充実したものにしていきましょう。

ワンちゃんが伸び伸びと遊べるドッグラン

庭の一角に設けた畑スペース

お孫さんとプール遊びができるスペースに整備
2024.09.09
外出や帰宅をスムーズに ~玄関回りの工夫~
毎日の生活で避けては通れない家事。
住まいに工夫をすることで、時間短縮を図ったり苦手な作業を省くことができます。
今回は外出時や帰宅時のストレスを軽減する玄関回りの工夫についてご紹介します。
玄関回りの工夫 実例
大きめの玄関庇で雨の日も安心

雨の日でも濡れることなく出入りできるように、玄関庇を大きめに設けました。
玄関と駐車スペースを隣接させると更にお出掛けが便利になります。
汚れを気にせず収納できる土間スペース
靴を履いたまま利用できる土間収納は園芸用品など外で使うものを置くのに便利です。
ハンガーパイプには上着だけでなく、雑貨などをハンギングしてインテリアに活用することもできます。

帰宅後すぐに手洗いできる間取りの工夫

玄関を入ってすぐの場所に洗面化粧台を設置しました。
帰宅後すぐに手洗いができ、来客時にも気兼ねなく使ってもらうことができます。
家の印象や使い勝手を大きく左右する玄関回り。
上記の実例以外にも、バリアフリー化や防犯性への配慮、床材や壁材などの内装材の工夫など、配慮するべきポイントはたくさんあります。
まずは現状の不満を解消するところから始めてみることをおすすめします。
2024.08.27
ショールームの上手な活用方法
住宅設備や建材などを選ぶ際には、各メーカーのショールームを上手く活用したいものです。
家づくりの計画がある人も、まだ具体的には決まっていない人も、段階に応じた活用の仕方をご紹介します。
計画が具体化していない段階の場合
近年のショールームは単なる商品の展示の場としてだけでなく、暮らしそのものを提案する場としての役割も担っています。
計画が具体的に進んでいない検討段階でも、新しい暮らしへのイメージを膨らます場として利用してみてはいかがでしょうか。


トータルコーディネートされた空間でトレンドを実感し、好みのテイストを見つける楽しみもあります。
暮らしの不満を解決することができる、最新の機器に出会えることがあるかもしれません。
家づくりのプランが決まっている場合
家づくりのプランが決まっていて商品を選択する段階においては、効率よく見学するための準備が必要です。
図面やたたき台のプランがある場合には持参し、実際に現場に取り付けることが可能なのかどうか確認してもらうようにしましょう。
スケールや現場写真を用意すると、さらに詳細な確認ができます。
こだわりや希望がある場合はリストアップして見学時に伝えておくと、必要のない商品まで案内してもらう手間が省けます。


実物を見てしまうと、よりグレードの高い商品を選んでしまい、当初の予算をオーバーしてしまうということはよくあることです。
家族で事前に話し合って、優先順位を決めておくことをおすすめします。
一日で何社かのメーカーを回る場合には、2社程度にとどめておくことが無難です。
一通りの商品を見るだけでも1~2時間は掛かり、思いのほか疲れてしまうことが多いようです。
見学時に気を付けること
休館日や混雑していてゆっくりと見学できない日時もあるので、見学時には予約をしてから訪問するようにします。
自由に見学したい場合には、その旨を伝えておくとよいでしょう。
靴を脱いで肌触りを体感できるスペースがある場合もありますので、脱ぎ履きがしやすい靴を履いていかれることをおすすめします。
見学するたびに新しい発見がありワクワクさせてくれるショールーム。
リフォームや新築の予定がある人もそうでない人も、気軽に訪れてよりよい住まいづくりの参考にしてみてはいかがでしょうか。
2024.06.28
畳を暮らしに取り入れてみませんか
近年、畳のある和室は減少傾向にある一方、根強い人気で畳にこだわったリフォームを希望される方も少なくはありません。
国産い草の畳表


外国産のい草を使った畳表が多い中、厳しい検査を受けて品質が保証された国産の畳表にこだわる方も。
中でも熊本県産は全国のい草の生産量のうちの90%を占めており、当社のお客様でも採用される方が多いです。
リビングに畳コーナー

リビングの一角に畳コーナーを設けるリノベーションも人気です。
小上がりの畳コーナーはベンチ替わりにもなります。
くつろぎスペースとしてだけでなく、ちょっとした作業を行う場としても大活躍です。
琉球畳でモダンに

半畳サイズの畳を市松模様に敷いた琉球畳は、モダンな印象です。
和に振り切るもよし、和洋折衷もよし。使い方次第でオリジナリティあふれる空間を作り出すことが可能です。
2024.06.07
洗濯を楽にするランドリースペース
毎日の生活で避けては通れない家事。
住まいに工夫をすることで、時間短縮を図ったり苦手な作業を省くことができます。
洗濯が楽になる工夫について実例と共にご紹介します。
洗濯を楽にするランドリースペースの実例
洗う→干す→畳むを一部屋で


洗濯機の設置場所に物干しバーと作業台を設け、洗濯にかかわる作業を一部屋で完結。
洗濯物の移動距離を少なくします。
干す場所の工夫で乾燥時間を短縮
吹き抜け部分をすのこ状の床にすることで、上昇気流を利用し洗濯物を早く乾かします。
日光の力も上手に取り入れます。


便利な機器の導入
エアコンや洗濯乾燥機、浴室暖房乾燥機などの力を借りるのもおすすめです。
外干しの手間を省き、天気が悪い日でも安心です。


洗濯の効率化を図るには、洗う→干す→取り入れるという流れをスムーズに行う必要があります。
また、日中あまり家におられない場合には、室内の適切な場所の物干しスペースを設けることをおすすめします。
2023.11.27
『これからの住まいと暮らしを考えてみませんか』 vol.8 余った部屋の活用への配慮

子ども部屋や和室など、
生活環境が変わり
使われなくなった部屋はありませんか。
趣味の部屋や収納スペースなどに
改修して有効活用することを
おすすめします。
子ども部屋や和室など、生活環境が変わり使われなくなった部屋はありませんか。
趣味の部屋や収納スペースなどに改修して有効活用することをおすすめします。

before

after
使われていなかった屋根裏スペースを改修しました。

before

after
濡れ縁で母屋と行き来ができる小屋を増築しました。
K様邸リノベーション

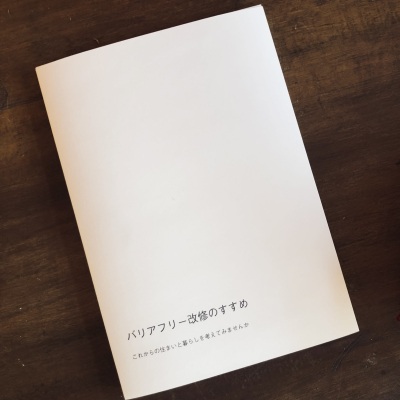
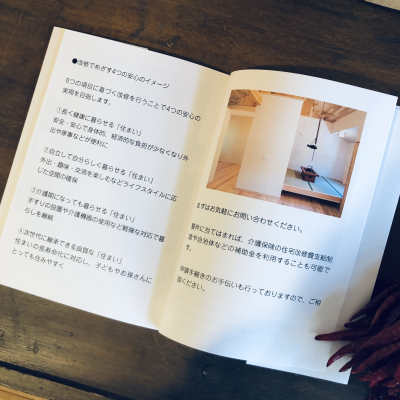
これからの住まいと暮らしを考えた改修をご紹介した冊子「バリアフリー改修のすすめ」をご用意しています。
ご興味のある方はお問い合わせくださいね。
2023.09.11
『これからの住まいと暮らしを考えてみませんか』 vol.7 光・音・匂い・湿度などへの配慮

人生百年時代と言われる現代。
今は元気でも、年を重ねるにつれて
体力低下が起きて、住まい方にも変
化が必要となってきます。
ご家族にとって、現在の住まいが安
全で快適な環境になっているのかど
うか、将来を想定して確認してみる
ことをおすすめします。

家で過ごす時間が増える高齢期においては、光や音などのストレスを感じることなく、快適に過ごすことのできる住環境はとても重要です。
窓の配置・大きさの変更や新設により、通風や明るさ、防音性の向上につなげます。

また、複数照明や間接照明などで落ち着いた雰囲気と必要な明るさの確保を両立します。
匂いや湿気が気になる場合には適切な場所に換気設備を設置するとよいでしょう。
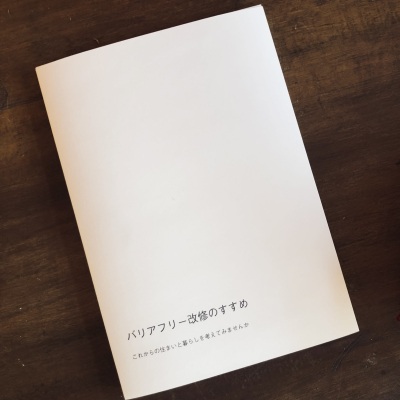
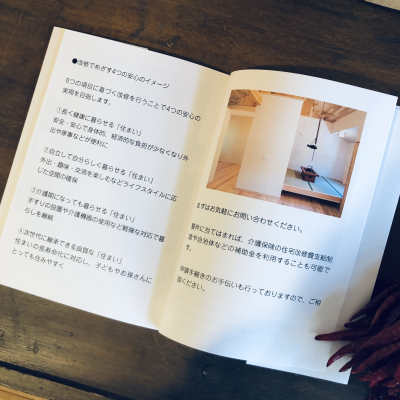
これからの住まいと暮らしを考えた改修をご紹介した冊子「バリアフリー改修のすすめ」をご用意しています。
ご興味のある方はお問い合わせくださいね。
2023.06.09
『これからの住まいと暮らしを考えてみませんか』 vol.6 設備の導入・更新への配慮

人生百年時代と言われる現代。
今は元気でも、年を重ねるにつれて
体力低下が起きて、住まい方にも変
化が必要となってきます。
ご家族にとって、現在の住まいが安
全で快適な環境になっているのかど
うか、将来を想定して確認してみる
ことをおすすめします。
便利な最新の設備機器を導入することは、安全・清潔な生活を送るための手助けとなります。
また、最新の設備は省エネルギーに配慮されており、ランニングコスト減につながることもあります。
おすすめのリフォーム

・火が出ないIHクッキングヒーターを導入することで、ガスコンロと比べて調理が安全に
・掃除のしやすいレンジフードの導入でお掃除楽々
・食器洗い乾燥機の設置で手間を軽減し節水にも

・浴室暖房乾燥機の導入で洗濯物を浴室内で乾燥でき、浴室を温かくしておくことで入浴時のヒートショックを回避

・外出時の利便性や防犯性の向上のため、電動シャッター・自動点灯照明・防犯カメラ・ドアホンなどを設置する
現在お使いの設備機器が10年以上経過している場合には、最新の機器に交換されることを検討してみてはいかがでしょうか。商品についてのご相談も受け付けております。
2023.03.06
『これからの住まいと暮らしを考えてみませんか』 vol.5 主要動線上のバリアフリーへの配慮

人生百年時代と言われる現代。
今は元気でも、年を重ねるにつれて
体力低下が起きて、住まい方にも変
化が必要となってきます。
ご家族にとって、現在の住まいが安
全で快適な環境になっているのかど
うか、将来を想定して確認してみる
ことをおすすめします。

加齢により身体機能が衰えると、小さな段差や暗い場所での転倒が起こりやすくなります。
家庭内事故をなくすためには、日常生活において移動しやすく転倒しにくい環境を作る必要があります。
おすすめのリフォーム
①床材の交換
・すべりにくい素材に交換
・歩きやすく転んでも衝撃を緩和する衝撃緩和畳の導入
②手掛かりや手すりの設置
・伝って歩くことができるよう動線上に設置
④段差の解消
・部屋同士の間仕切りをなくしひと続きの部屋にする
・ドアの下枠を段差のないものに交換
・床のかさ上げによる部屋間の段差解消
⑤収納スペースの確保
・物につまずかないよう各部屋に十分なスペースを設ける
⑥コンセントの位置を移動
電化製品のコードに足をひっかけることがないようにコンセントの位置の移動や露出のない配線ルートを確保


生活上で危ないと感じた場所や一日のうちで最も長く過ごす場所から見直しましょう。
事故の予防だけでなく活動的な生活を送ることにもつながります。
2023.01.26
『これからの住まいと暮らしを考えてみませんか』 vol.4 日常生活空間の合理化

身体的な負担をできるだけ少なく
日常生活を送るには、
生活空間の合理化を行う必要があります。
移動のための距離が遠いと感じるようになったり
階段の上り下りに不安がある場合には、
寝室などの日常的な生活空間を
1階に移動することをおすすめします。
また、お子様の独立などで家族の人数が減り、
使われていない部屋がある場合には、
複数の部屋をつなげてひとつの大きな部屋に
することを検討してみてはいかがでしょうか。
よく利用する空間が広くなることで、
家の中でゆったりと過ごすことができます。

おすすめのリフォーム
①階段の上り下りに負担を感じる場合
・洗濯物を干す際の負担を減らすために物干し場を2階から1階に移動
・生活空間を1階(同じ階)に集約させる
②夜間のトイレが心配な場合
・トイレを寝室の隣に配置する
・トイレに近い場所に開口(出入口)を設ける
③室内でつまずくことがある場合
・床の段差をなくしひと続きの広い空間にする
・ドアの下枠を段差のないものに替える
日常でよく使う空間の障害物をなくしていつまでも安全に過ごせるようにしましょう。
2022.11.25
新築 vs リノベーション
古くなった住宅を新築に建替えるのかリノベーションするのかで迷われる方は多いと思います。
どちらがよいのかを判断する際の参考に、それそれのメリット・デメリットを紹介します。
リノベーションとは
既存の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性能を向上させたり価値を高めることを言います。
 メリット
メリット
新築のメリット
1.間取りが自由でライフスタイルに合わせた計画が可能
2.ローンや保険審査に通りやすい
3.耐震性や省エネ性能が高くなる
リノベーションのメリット
1.愛着のある建物を壊さなくてもよい
2.税金面の負担が軽減できる
3.予算に合わせて内容を選択できる
新しく建替える場合は一からのスタートで家づくりの自由度が非常に高いことが大きなメリットです。また、現行の建築基準法に沿って建てるので、ローンや保険審査に比較的通りやすく、より性能の高い家を建てることができます。
一方、リノベーションの場合、思い入れのある家を完全には壊してはしまわずに、味わいのある材料を残すことが可能です。また、建築確認申請を行わなければ基本的に固定資産税はもとのままで、その他不動産取得税や都市計画税などの税金が軽減できます。予算に合わせてリノベーションの内容を選択できるのもメリットです。
 デメリット
デメリット
新築(建替え)のデメリット
1.解体費用がかかり総費用が高額になる
2.各種税金が高額になる
3.工事期間が長い
リノベーションのデメリット
1.既存住宅の構造によっては間取りに自由が利かない
2. 構造補強を含めると新築より高額になるケースもある
3.基礎などの主要構造物を替えない場合強度に不安が残る
建替えのデメリットは解体費用がかかることです。また、不動産取得税や固定資産税などの税金がリノベーションと比べて高額になる場合が多くなります。一からの工事で工事期間が長くなり、仮住まいにかかる費用も考慮する必要があります。
リノベーションの場合は既存住宅の構造によって制約があり、間取りなどが自由にならないことがあります。また、現状によっては補強に手間がかかり費用が高額になるケースもあります。予算の都合で主要構造物を替えない場合には、強度や性能に不安が残ることもデメリットです。
建替えとリノベーションのどちらがよいのかは一概には言えず、悩まれる方も非常に多いです。当社では現状の建物の状態やご家族の事情などを考慮して、ご自身に合った選択をしていただくお手伝いをしています。
当社の施工事例もぜひ参考にしてみてください。↓